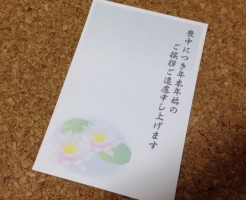お正月に年賀状を送るというのは、日本の素敵な習慣の1つです。
ですが、年賀状というのは、お祝いの気持ちがこもった贈り物。そのため、親類が亡くなった年などは、年賀状を出さない風習があり、これが喪中と呼ばれています。
では、そんな喪中に捉えられるのは、一体どこまでの親類なのでしょうか?範囲が難しいところですよね。また、いつまでに亡くなったことが喪中にあたるのか。その期間も難しいポイントです。
そこで、それらの点について調べてみました!
喪中と考えられる範囲
親類が亡くなったら、誰でも彼でも喪中、というわけではありません。一般的に喪中と考えられるのは、2親等までのごく親しい続柄の場合のみです。つまり、自分の配偶者、両親や祖父母、子供、孫、あとは兄弟といったところですね。
ですが、もちろんこれだけに限る必要もありません。例えば甥っ子や姪っ子、叔父、伯母などが亡くなった場合、同居していたり、別世帯でもごく親しい間柄であれば、喪中と考えても良いでしょう。
家族同然の付き合いの方が亡くなったのに、何事も無かったかのようにお祝いをするというのは、なんだか悲しい気持ちになってしまうものです。
喪中の範囲に厳密な決まりがあるわけではなく、近しい親類の中で、自分が喪に服すべきだと考える方が亡くなれば喪中と考えれば良いですね。ある程度親しい親戚で、故人に対する特別な想いがあれば、喪中とする方が多いようです。
喪中期間は?
喪中の範囲が分かったら、次に気になるのが喪中期間です。では、親類が亡くなってからどれくらいの期間が過ぎていれば、喪中は明けているのでしょうか?
これも、亡くなった方との関係性の深さによってある程度違ってきます。基本的に、ごく親しい配偶者、親子、兄弟といった間柄であれば、1年程度を喪中とします。ですが、中には「子供の服喪期間は3~6か月」「兄弟の服喪期間は30日~3か月」という期間の設定もあり、これを参考にする方もいらっしゃいます。
もちろん、こういった決まりに従っても大きな問題はありません。ただし、世間的には「子供が亡くなって1年も経っていないのに年賀状?」と感じられてしまうかもしれませんね。
喪中の期間については、決まり事を重視するよりも、その地域の方々がどのような感じで行っているかをリサーチしておいたほうが良いですね。
自分だけの考えで喪中期間を決めてしまうと、周囲に変に思われてしまう可能性も無いとは言い切れません。地域のごく親しい方や、親など頼れる方によく相談して、喪中とする期間を決定しましょう。
喪中ハガキを出すなら
喪中となった時に、まず行わなければならないのは、「喪中なので、年賀状が出せません」ということを伝える喪中ハガキの発送です。この喪中ハガキは、一体どの範囲まで出す必要があるのでしょうか?
これに関しては、毎年の年賀状をいただく方々や、相手からの年賀状は無くても、こちらからは毎年出しているという方々、全員に送りましょう。
「相手から来ないから、別に喪中を伝える必要は無い」なんてことはありません。「喪中ハガキも年賀状も来ないけど、元気にしているのか」と、相手に心配をかけてしまうことにもなりかねないので、きちんと送るようにしましょう。
また、もう1つ悩むのが、「相手も喪中で喪中ハガキを受け取った場合」ですね。この場合にも、きちんとこちらからも喪中であることを伝えるハガキが必要となります。
ただし、ごく親しい身内で、日ごろから交流がある方の場合には、喪中ハガキを出さないことも多いようです。そういった方の場合には、会ったときに「今年は喪中だから」と伝えておくと良いですね。
まとめ
喪中の範囲や期間といったものは、特に厳密な決まりというものはありません。かなり親しい間柄の親類でない限り、結局は「喪に服する気持ち」によって、自分で判断することになります。
それから、地域によっても多少の風習の違いがありますので、この点も事前にチェックするようにしておくと良いですね。周囲の親しい人に、喪中の際にはどうすべきか、アドバイスをもらうのが1番失敗の無い方法だと言えます。